栄養室
栄養とくとく話
2026年3月広報誌掲載
2026年1月広報誌掲載
冬の時期に食べたくなるのが『鍋』です。鍋には水炊きから鍋の素(味噌やキムチ、豆乳など)、しゃぶしゃぶやすき焼きなど様々あります。そんな鍋ですが、気になるのが塩分です。塩分の取り過ぎは、高血圧や腎臓への負担、心臓病や動脈硬化など様々な病気のリスクを高めます。鍋を食べる時は塩分を取り過ぎないように工夫しましょう!
2025年11月広報誌掲載
過ごしやすい秋の夜長、夕食が遅くなったり寝る前に夜食を食べたり、夜更かししたりなど、生活リズムが乱れていませんか?
【夜の食事が太りやすいとされる理由は複数あります】
① 夜間帯は活動量が少なくなるためエネルギーが消費されにくい!
→消費されない余分なエネルギーは体脂肪として蓄積される。
② 体内時計の調節機能を担う“BMAL1(ビーマルワン)”と呼ばれるたんぱく質が脂肪合成を促進する!
→BMAL1は22時〜深夜2時に最も多くなり、日中の食事と比べて夜食は太りやすい。
③ 睡眠不足は食欲を増進させる!
→睡眠時間が短いと、食欲を抑えるホルモンのレプチンが減少する一方で、食欲を増進させるホルモンのグレリンは増加する。
夕食が遅くなってしまう場合は、脂質を抑えた消化にやさしいメニューを選びましょう。
また、夕食を2回に分けて摂る分食もおすすめです。先におにぎりなどの主食を食べ、後からおかずなどの副菜を摂りましょう。ゆっくりよく噛んで食べることは、脳の満腹中枢を刺激し、食べ過ぎ防止になります。秋太りしないよう、規則正しい生活を送りましょう。
2025年9月広報誌掲載
あなたの骨は大丈夫?骨粗しょう症予防のために食事でできること
10月20日は、世界骨粗しょう症デーです。
「骨粗しょう症」とは骨の密度が減って骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。 国内では約1,280万人が骨粗しょう症と言われており、年々増加傾向にあります。また、骨折を一度起こすと、再び骨折するリスクが2~4倍高くなったり、要介護状態や寝たきりの原因になったりします。そのため、日頃から食事や生活を見直し、骨粗しょう症になるリスクを低下させましょう。
【骨を強くするために必要な栄養素】
☆1日3食、主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスのよい食事を基本とし、上記の栄養素を取り入れることがおすすめです。
2025年7月広報誌掲載
朝、時間がなかったり、なかなか起きられなかったりと朝ご飯をちゃんと食べられていない時がありませんか?
【朝ごはんを食べるといいこといっぱい】
①脳の活性化
脳はブドウ糖をエネルギー源としています。朝ごはんを食べる事で脳が働き、集中力や記憶量が増します。
②便秘予防
食事を摂ることで胃や腸が刺激され、大腸がぜん動運動を開始し排便が促されます。
③肥満予防
朝ごはんを食べないと昼ごはんを食べた時に血糖値が一気に上昇し、肥満になりやすくなります。
④体内時計の調整
私たちの体には体内時計と呼ばれる機能があり25時間周期でリズムが刻まれています。1日が24時間なのでずれが生じてしまいます。そこで朝食をとると体内時計がリセットされて1日の生活リズムが整います。
【朝ごはん、どんなものを食べたらいいの?】
栄養バランスのよい食事を目指しましょう。
主食…ご飯やパンなど炭水化物
主菜…お肉や魚などのたんぱく質
副菜…野菜やキノコなどビタミンやミネラルがとれるおかず
※牛乳や果物もプラスしましょう
朝ごはんは1日の始まりです。生活スタイルに合わせた朝食を習慣づけていきましょう。
2025年5月広報誌掲載
「日本人の食事摂取基準2025年版」より、健康の保持・増進、生活習慣病の発症予防の目的から、炭水化物の目標量は1日の摂取エネルギーの50~65%です。
2025年3月広報誌掲載
たんぱく質+運動で筋肉を維持しましょう!
筋肉量は、加齢とともに筋肉の合成力が落ちるため減少しやすくなります。筋肉量が減ると基礎代謝量も落ち、肥満や生活習慣病などの様々な病気を引き起こす原因となります。
〈筋肉を維持・増加させるためポイント〉
■良質な「たんぱく質」を摂取する
筋肉を作るために必要な栄養素は「たんぱく質」です。特に良質なたんぱく質を多く含む肉・魚介・大豆製品・卵類を毎食揃えましょう。 (※体の大きさや身体活動レベルによって必要量には個人差があります)
■「運動習慣」を身に付ける
上記のたんぱく質の摂取とともに運動をセットで取り入れることが鉄則です。ウォーキングや筋トレなど自分の体力やライフスタイルに合った量や強さの運動から取り組み、習慣化しましょう。
2025年1月広報誌掲載
クリスマスに年末年始と、お酒を飲む機会が多い時期になりました。人が集まる賑やかな場所ではついつい飲みすぎてしまうことも。飲酒に関するガイドラインでは、少量の飲酒であっても高血圧や男性の食道がん、女性の脳卒中など特定の疾病において発症リスクが上がることが記載されています。よって、1日の純アルコール量の適正量である20gを守っていても、全ての疾患を絶対に予防するとは言い切れません。しかし、アルコールが及ぼす身体への影響は年齢、性別、遺伝など個人差がありますが、純アルコール量の適正量を守り、自分に合った飲酒量を考えることで、その他多くの疾患にかかる可能性を減らすことができます。健康に配慮した飲酒を心がけましょう。
(※持病がある方は医師と相談の上、飲酒の可否を決めましょう。)
2024年11月広報誌掲載
味がしない…、疲れやすい…。それって味覚異常のサインかも?
亜鉛とは
からだの健康維持に欠かすことのできない「必須微量ミネラル」です。食が細くなりやすい高齢者は、亜鉛不足を招くケースがあります。また、加工食品に多く含まれるポリリン酸は亜鉛の吸収を妨げるため、コンビニやスーパーなどの偏った食生活を送っている方も、亜鉛不足に注意が必要です。
亜鉛が不足すると
味覚障害、食欲不振、貧血、免疫機能低下、皮膚炎、骨粗鬆症などを引き起こします。
特に高齢者は寝たきりによる血流不良・栄養状態の低下・失禁による湿潤が原因で「褥瘡(じょくそう)」(床ずれ)を起こしやすく、その予防や治療にも亜鉛がとても重要とされています。
亜鉛を含む食品
牡蠣、カシューナッツ、豚レバー、牛赤身、卵など、
ピタミンCや動物性たんぱく質食材と一緒に摂取すると吸収率がUPします。
2024年9月広報誌掲載
9月に入っても暑い日が続き、食事がすすまない方も多いと思います。食欲アップには食事の美味しさのもとである「うま味」が欠かせません。「うま味」とは、塩味、甘味、酸味、苦味と同じ基本味の一つです。また、うま味成分は何種類もありますが、知られているのが、「グルタミン酸」、「イノシン酸」、「グアニル酸」の3つです。
【うま味の相乗効果】
特定の組み合わせで、単独で使うよりもうま味が7~8倍に感じられると言われています。その現象を「うま味の相乗効果」と呼びます。また、減塩料理への活用も効果的です。うま味を利用することで、食事の満足度が上がり、美味しさを損なわずに減塩につなげることが出来ます。
2024年7月広報誌掲載
主食のご飯は何を選んでいますか?
炭水化物は3大栄養素のひとつで、脳や体を動かすといった主にエネルギー源として利用される大切な栄養素です。体内の消化酵素で消化できる「糖質」と消化されない「食物繊維」に分けられます。主食を摂ることは、筋肉量を維持するためにも大切なため、糖質の量が気になる方は「ご飯の種類」を変えて食物繊維を増やしてみてはいかがでしょうか?
『白米』もちもちした食感で甘味がある。不溶性食物繊維が主に含まれているが、糖質の代謝を助けるビタミンB1が少ないため、他の食品から補うことが大切。
『玄米』精米していないお米のことで、白米よりビタミンB群が多く含まれている。食感がやや硬い。
『麦ごはん』食物繊維などが多い。中でも水溶性食物繊維のβグルカンという物質は血糖値の上昇抑制や血中コレステロールを低下させる作用が期待されている。麦にも用途により種類があるが、加工しても食物繊維の量が減らないのが特徴。
『雑穀米』玄米、あわ、キビ、もち麦などを白米に混ぜ込んだもので種類が豊富。食物繊維等を増やすことができる。
『こんにゃく米』こんにゃくをお米の形に加工して、お米と一緒に炊いて食べるもの。エネルギーと糖質を抑え、食物繊維が多くなる。中でも水溶性食物繊維のグルコマンナンは血糖値の上昇抑制や血中コレステロールを低下させる作用が期待されている。
『カリフラワーライス』糖質は白米の1/16、ビタミン・ミネラルなどが豊富。お米ではないため、さっぱりとしている。
2024年5月広報誌掲載
加齢とともに変化する「味覚」について
「味覚閾値」という言葉を知っていますか?これは人が味を感じるのに必要な刺激量の最低濃度を指します。歳をとると味を感じる味蕾の細胞が減少するため「味覚閾値」は高くなります。つまり、味を感じるために必要な刺激量(甘味・塩味・酸味・苦味)が増える、より濃い味付けが必要になるということです。知らず知らずのうちに濃い味付けを好むようになっていませんか?塩分の取りすぎは高血圧を引き起こし、糖尿病患者さんは砂糖やみりんの使い方に注意が必要です。料理の味付けやメニューの選び方を見直しましょう。
〈薄味でも美味しく食べるポイント〉
①よく噛んで食べる…味蕾は液体に反応するため、咀嚼して唾液と食物が混ざることで味を感じやすくなる
②酸味を生かす …酸味は塩味・甘味と比べて閾値が低いので味を感じやすい
③食生活を整える …食生活が乱れると味蕾の細胞に必要な亜鉛が不足し、味を感じにくくなる
2024年3月広報誌掲載
葉酸が妊娠のごく初期に欠乏すると、胎児の神経管閉鎖障害の危険性が高まると言われています。葉酸には他にも動脈硬化の予防に重要な役割を果たしていることがわかってきました。
葉酸は「ホモシステイン」という物質をメチオニンに変換する時に必要となる栄養素の一つだからです。
ホモシステインという物質が血中に多くなると、動脈硬化や血小板の凝集、血栓形成の促進などによる血管系疾患や骨粗鬆症の発症に関係するなど、健康リスクが高まってしまいます。
年齢問わず、葉酸をしっかりと摂取することが大切です。
2023年1月広報誌掲載
食事を『咀嚼』することの重要性
日本人の咀嚼回数は食生活の変化と共に低下傾向にあり、1回の食事あたり戦前は約1400回だったのに対し、現代は約600回と言われています。
咀嚼することのメリット
○肥満防止…咀嚼回数が少ない=早食い は肥満リスクが倍以上に。
満腹中枢の正体は脳神経のヒスタミン。内臓脂肪を減らす働きがあります。
○脳の発達…脳への血流量が増し、脳細胞の働きが活発に。認知症の予防にもなります。
○歯の健康…唾液の分泌量が増えることで、虫歯や歯周病を予防します。
○代謝促進…消化器官への血流量が増え、消化活動によるエネルギー消費量が増えます。
一年間よく噛む事を意識した人とそうでない人の差は約11000kcalです。
咀嚼回数の目安は1口30回です。あえて咀嚼を要する食材を選ぶのも良いでしょう。
ゆっくり食事を楽しみながら、マスク生活で衰えやすい口全体の筋肉を鍛えましょう。
2023年11月広報誌掲載
年末年始はなぜ太る?正月太りしないために気を付けること
年末年始はさまざまなイベントがあり、体重が増加してしまったと悩む人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年末年始の食生活の注意点をご紹介します。
① 食べ過ぎない。飲み過ぎない
長い休みは豪華な料理やアルコールなどを食べる機会が増える時期です。暴飲暴食を繰り返すことで体重増加につながる可能性があります。
② おせち料理はバランスを考える
おせち料理は砂糖や塩分が多く、偏りがちです。雑煮は具だくさんにし、野菜や海藻類もたっぷり摂りましょう。
③ 3食食べる
起床時間が遅くなり、生活リズムが崩れやすくなります。だらだらと食べてしまったり、朝食を欠食することがあります。生活リズムを整え、3食食べましょう。
④ 果物は箱買いしない
冬は果物がおいしい時期です。特にみかんは箱で買うとつい多く食べてしまいます。箱買いをしないで必要分のみ買う事もひとつの方法です。
新しく迎える1年のためにも、未然に防ぐ事が大切ですね。
2023年9月広報誌掲載
あなたは大丈夫?「秋バテ」対策をしましょう!」
暑さも落ち着く9月下旬頃から夏バテに似た症状が出てくることがあります。
これを「秋バテ」と言い、夏の間にためてしまった疲れと体の冷えにより、自律神経の乱れと血のめぐりが悪くなることで以下の症状が現れます。
〈秋バテの主な症状〉
・体がだるい ・疲れやすい ・食欲がない ・胸焼けや胃もたれ ・めまい、立ちくらみ
・肩こりや頭痛がする
〈秋バテ対策ポイント〉
①冷え対策 ②質の良い睡眠 ③適度な運動で体を動かす ④体を温め、ビタミンやミネラルが豊富な食材を取り入れる ☆体を温める食べ物…しょうが、にら、ねぎ、唐辛子
2023年7月広報誌掲載
マグネシウムは私たちの体に必要なミネラルで、主に骨や歯を作るのに役立つ栄養素です。他にも神経機能、筋肉の収縮弛緩、エネルギー代謝、さらにホルモンの分泌などに関与しています。
マグネシウムが長期で不足すると、骨粗鬆症、心疾患、糖尿病のような生活習慣病のリスクが高まります。
また、便秘薬にマグネシウム剤を使用するように、マグネシウムには水分吸収を高め、水を含みやすくなることで、便がやわらかくなります。そのため食物繊維などと同時に摂れば、便のカサを大きくすることもでき、腸のぜん動運動を助けて便秘解消に繋がることができます。
サプリメントからの摂取もできますが、過剰摂取はしないように注意しましょう。
また、腎機能が悪い人は注意が必要なため、主治医に確認しましょう。
2023年5月広報誌掲載
近頃メディアなどで激辛料理を耳にしますが、辛味成分は身体にどんな影響を与えるのでしょうか?そもそも「辛味」は味覚の五味(甘味・塩味・酸味・旨味・苦味)に含まれず、痛覚に近い感覚とされています。辛味成分の中でも代表的なものは、唐辛子に含まれる「カプサイシン」です。
○痛み・灼熱感をもたらす
カプサイシンが引き起こす灼熱感は口腔内から気管支や消化管全体に及び、
強い刺激で気管支収縮を引き起こし、息切れや咳が出ます。
また、肛門部にカプサイシンの受容体が多く存在するため痛みが生じます。
○消化管への影響
少量摂取では胃酸分泌を抑制するため胃粘膜を保護しますが、多量摂取では感覚神経の受容体が機能不全を起こし、胃痛や下痢、胃食道逆流症などの消化器症状を起こすことが動物試験で報告されています。
○代謝への影響
消化管で吸収されるとアドレナリンが分泌され、体温をあげて発汗を促し、脂肪やエネルギー代謝を促進させます。
具体的な上限量は定められていませんが、辛味成分の極端な多量摂取は避け、
美味しく食べられる常識的な範囲で、料理に生かしましょう。
2023年3月広報誌掲載
~時間栄養学で体内時計を整える~
近年、私たちの体には体内時計が備わっており、食事や生活リズムによって体内時計が動くことが分かりました。今回は、「いつ」食べたら良いかという時間の概念を取り入れた「時間栄養学」をご紹介します。
2023年1月広報誌掲載
近年は多くの食品パッケージで“○○ゼロ”や“○○オフ”など特定の栄養素が強調された表示を目にしますが、
その意味を正しく理解し購入できていますか?
食品表示法では強調表示について、
特定の栄養素を①含まない旨、②低い旨、③低減された旨の3つに大別しています。
また、100mlあたりの基準であるためカロリーゼロの飲料水をペットボトル1本(500ml)飲むと、
砂糖小さじ2杯分のカロリー(約24kcal)を摂ってしまう可能性があります。
よって、これらの表示があっても多量に摂取すれば、結果としてエネルギー摂取量が増えることになります。
“○○ゼロ”や“○○オフ”といった食品に頼り過ぎず、食事全体のバランスや量を考えることが大切です。
2022年11月広報誌掲載
骨を構成する成分のうち、カルシウムは重要なミネラルです。
日本人は不足しがちになっています。
そこでビタミンDと一緒に食べることでカルシウムの吸収率を上げましょう。
ビタミンDを増やすには・・・
① 食品から・・・鮭やうなぎなどの魚類、きのこ類に多い
② 日光から・・・紫外線が皮膚に当たることでも産生される。
(目安→夏の昼間:約5分以上、冬の昼間:約20分以上)
※5.5μg分のビタミンD
1日あたりのビタミンDの目安量は『8.5μg』(例:食品から3μg+日光5.5μg)
鮭(焼き)80g(30μg) さんま(焼き)100g(13μg) 赤身まぐろ70g(2.8μg)
きくらげ(油炒め)10g(3.8μg) まいたけ(油炒め)10g(0.7μg) 椎茸(油炒め)10g(0.05μg)
2022年9月広報誌掲載
持続可能な開発目標(SDGs)が2001年に策定されました。日々の食生活を見直して食品ロスを削減することで、SDGs達成に貢献できます。一人ひとりができる食品ロス対策は「食べ物を捨てない」以外にもいくつかの方法があるので、できることを見つけて実践してみましょう。
輸送エネルギーやコストの削減を図ることにもつながります。
まずは自分や家族の食生活を見直してみましょう。
2022年7月広報誌掲載
野菜ジュースは体に良い?野菜の代わりになる?
手軽に摂取できる野菜ジュースは体に良いイメージがありますが、
実際のところ本物の野菜と比べて同じだけの栄養素は摂れるのでしょうか?
野菜ジュースは、加熱して水分を飛ばす「熱濃縮」を行なった後に、水分を加えて元の状態に戻す「濃縮還元」が行われます。熱濃縮で加熱に弱い水溶性ビタミンや、野菜を絞る工程で不溶性食物繊維は搾りカスと共に捨てられてしまいます。そのため、同じ量の野菜ジュースと本物の野菜では摂れる栄養素に違いがあります。
また、野菜ジュースは砂糖を添加したもの、果物の割合が多いものがあるため、たくさん摂取するとエネルギー過多となり、体重を減らしたい人や糖尿病患者さんは注意が必要です。本物の野菜と違って咀嚼をしないので、脳が「食べ物を食べた」と認識せず満腹感も生まれません。
よって、食事は本物の野菜を摂取するよう心がけ、野菜ジュースは野菜が摂れない時の補助食品としての認識にとどめておきましょう。特に、旬の野菜は栄養価が高いため、積極的に料理に取り入れて毎日の食事を楽しみましょう。
2022年5月広報誌掲載
乳酸菌の種類?腸に効きそうなのはどっち?
腸内環境を整えようと思ったらまずヨーグルトの「乳酸菌」を思い浮かべませんか?
乳酸菌は腸内で大腸菌など悪玉菌の繁殖を抑え、腸内菌のバランスをとる役割があるため、
便通の改善だけでなく、コレステロールの低下や免疫機能を高めがんを予防するなど様々な働きがあると言われています。
そんな乳酸菌には「植物性」と「動物性」があります。
植物性乳酸菌 <漬物、味噌、キムチなど>
過酷な環境で育ってきた菌なため、生きたまま腸へ届きやすい
熱に弱いため、加熱しない調理法がおススメ
塩分が高い物が多いため、食べすぎには注意!
動物性乳酸菌 <ヨーグルト、チーズ、乳酸菌飲料など>
強酸性の胃の中を突破できず、死んでしまうものが多い
しかし、死菌であっても、腸内細菌のエサになるので有益!
腸内環境が変化するには2週間以上継続して食べる必要があります。
バランスの良い食事と継続的な乳酸菌摂取を目指しましょう!
2022年3月広報誌掲載
仕事などの合間で時間がなく、
手軽に食べられるうどんやそばだけなど栄養バランスの偏った昼食が続いていませんか?
賢く上手に選ぶことで生活習慣病の予防が期待できます。
1. 望ましい食事の基本は
「主食・主菜・副菜」が揃うことです。
2. 組み合わせのひと工夫
丼ものや麺類を選ぶ場合には、その他に小鉢(野菜やきのこ、いもや海藻類)を1品追加して、
野菜類をとりましょう。
3. 栄養情報の活用
献立には栄養成分表示があるものもあります。
エネルギーや塩分などが記載されていますので、見比べてから料理を選びましょう。
栄養情報の活用1日の食事のうちの一部なので、そのほかの食事とのバランスを考えることも大切です。
2022年1月広報誌掲載
寒い日が続き、体が冷えると動くのも億劫になりがちですね。
食べ物で体を温めるのも、防寒対策の一つになります。
また、血行が良くなると、肩こりや疲れといった体の不調も解消できます。
■体を温める食材は以下の物があります。
・ 生姜、香辛料、にんにく
加熱した生姜に含まれるショウガオールや唐辛子に含まれるカプサイシンには、血液を体の隅々までいきわたらせ、体を温める働きがあります。
・人参、長ねぎ、玉ねぎ、ごぼう、れんこん、かぼちゃ、にらなど
冬が旬、地面の下にできる野菜、黒・赤・オレンジ色をしたものは体を温めるビタミンやミネラルが豊富に含まれています。
■一方、体を冷やす食べ物や習慣は・・・
×体を冷やす食材をよく食べる
夏が旬の野菜や果物は体を冷やす性質があります。
調理方法を変えたり、食べる量を少し控えたりしましょう。
×朝ごはんを抜く
朝ごはんを食べないと体温が上がらず、低体温になりがちです。
一日3食、規則正しく食事を摂るように心掛けましょう。
×偏食しがち
野菜を食べない、米やパンなどの炭水化物やインスタント食品ばかりといった栄養バランスの乱れが続くと
たんぱく質、ビタミン、ミネラルの不足が起こり、冷えが悪化しやすくなります。
体を温める食材を上手に利用し、体を冷やす習慣は控えて、寒い冬を乗り切りましょう!
2021年11月広報誌掲載
食事を摂ると体内に吸収された栄養素が分解され、その一部が体熱となって消費され代謝量が増えます。この代謝の増加を食事誘発性熱産生(DIT: Diet Induced Thermogenesis)といいます。
DITで消費されるエネルギーは1食の摂取エネルギーの10%程度とされていますが、栄養素ごとに生産量は異なり、たんぱく質においては約30%がDITによって消費されるため、たんぱく質含むバランスの食事でDITが維持されます。また、加齢や運動不足で筋肉が衰えると、基礎代謝が低下するだけでなくDITも低下します。逆にトレーニングで筋肉を増やすとDITは高くなるとされています。
【DITによるエネルギー消費量】
・「たんぱく質」・・・摂取エネルギーの30%
・「炭水化物」・・・摂取エネルギーの6%
・「脂質」・・・摂取エネルギーの4%
2021年9月広報誌掲載
気温や湿度が上がり食べ物が傷みやすい季節、この時期に便利な野菜の保存方法が「冷凍」です。美味しさや鮮度をキープする保存のコツを紹介します。
【冷凍方法は2種類】
①生のまま冷凍する:使いやすい大きさにカットして、ラップしてフリーザーバッグに入れる。
きのこ、かぼちゃ、人参、キャベツなど
②下茹でしてから冷凍する:少し固めに茹で粗熱を取り、水分をしっかり切る。ラップしてフリーザーバッグに入れる。
ブロッコリー、ほうれん草、小松菜など
アルミのバットやアルミホイルにのせて、急速に冷凍します。その後の調理方法は、解凍せずに、冷凍のまま調理します。1週間を目安にできるだけ早く使い切りましょう。
【冷凍に不向きな食材】
野菜類全般冷凍出来ますが、水分の多いきゅうりやじゃがいもなどの芋類は食感が悪くなり、不向きです。上手に保存して、使い残した野菜、多めに買った野菜もムダなくおいしく食べましょう。
2021年7月広報誌掲載
暑さも増し、夏本番が近づきスーパーにも色々な果物が出てきました。実は熟すのを待たなくてはいけない果物と買ってすぐに食べることができる果物の2つに区別できることを知っていますか?熟すのを待つ果実を「クライマクテリック型」といい、すぐに食べることのできる果実を「非クライマクテリック型」といいます。
「クライマクテリック型」果実 | 「非クライマクテリック型」果実 |
バナナ、桃、りんご、梨、あんず、メロン、キウイフルーツ、マンゴー、パパイヤ、 | 柑橘類、ベリー類、すいか、いちじく、 |
ほとんどの果物は成熟過程において、植物ホルモンの一種であるエチレンガスが発生し、濃度が増加することにより、成熟が進みます。
「クライマクテリック型」の果実は、収穫後もエチレンガスによって追熟するため甘さが増します。しかし、せっかく買ってきたのにすぐに食べることができないのは困るという時に食べごろを早める方法があります。りんごなどエチレンの発生量が多い果物を近くに置いたり、袋の中に一緒に入れたりすることで追熟を促すことができるのです。
一方、「非クライマクテリック型」の果実は、収穫後にエチレンガスを放出しないため、しばらく置いても甘さが増すことはありません。よって、収穫後は追熟することなく、鮮度が落ちていくだけなので、早めに食べ切るようにしましょう。
2021年5月広報誌掲載
疲れた時、ついつい甘いものが欲しくなりますよね。これは、脳や体にエネルギーが届けられ、一時的に元気になったように感じるためです。しかし、糖質を摂取し急激に上がった血糖値は、インスリンの働きにより一気に下がり、血糖値の急激な変動(血糖スパイク)を起こします。これを繰り返すと、さらにだるさや疲れを引き起こす原因となります。
そこで、おすすめなのが必須アミノ酸であるトリプトファンを含むたんぱく質の積極的摂取です。筋合成を促進し、身体の疲れを回復する効果があります。また、トリプトファンには幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの働きを助け、脳疲労に効果的とされています。低糖質で蛋白質豊富な食材を取り入れ、疲れを上手に解消しましょう!
トリプトファンたっぷりのおすすめ食材
チーズ、ヨーグルト、納豆、牛乳、豆腐
※腎機能が低下している方、生活習慣病のある方は主治医にご相談ください。
2021年3月広報誌掲載
だんだんと暖かな日が増え春へと近づく3月。春野菜も見かけるようになってきました。
その時期の旬の野菜は味が美味しいことはもちろん、栄養価も高いことが特徴です。
また、免疫力を高め、体内の機能を調整する成分も含んでいます。
春野菜に多く含まれる栄養素
【苦味成分】
菜花やふきのとうには苦味の成分である「植物性アルカロイド」が多く含まれています。
腎臓の機能を向上させ、老廃物を体の外に出すデトックス作用や、新陳代謝促進作用があります。
【香り成分】
明日葉やせり、セロリといったセリ科の香りには、精油成分の「テルペン類」が多く含まれています。
血行促進や抗酸化作用、ストレス緩和に効果があります。
野菜本来の旬のものと旬ではない時期に栽培や収穫されたものでは、栄養価が数倍も
違うものもあります。
ぜひ、各季節の旬野菜を料理に取り入れて楽しみましょう。
2021年1月広報誌掲載
長引くコロナ禍でストレスを抱えている方は多いのではないでしょうか?「イライラやストレスを解消するにはカルシウムを摂れば良い!」とよく言われますが、本当でしょうか?
カルシウムには脳神経の興奮を抑える働きがありますが、厳密にシステム管理されているため、常に一定の供給量になるように管理されています。つまりカルシウムを含んだ物を食べないからといって、すぐにイライラすることはありません。
ただし骨からカルシウムが出庫されてばかりでは、不足状態に陥ってしまいます。そのようにならないためには、
① カルシウムを多く含んだ食べ物(牛乳・小魚・大豆製品など)
② カルシウムの吸収を良くするために必要なビタミンD(魚介類・卵類・きのこ類など)
③ カルシウムを骨にするビタミンA(緑黄色野菜など)
を摂ると良いと言われています。バランスの良い食生活をして、これらの食品を摂るように日頃から心がけておくこと大切ですね。
2020年11月広報誌掲載
長期化するコロナ禍、私たちは様々なストレスを感じて生活をしています。ストレスの影響は、食欲低下や過食など食事量の変化として表れることがあります。低体重だけでなく、過体重でも免疫機能に悪い影響を与えることがわかっており、感染予防の観点からも適正な体重の維持が大切です。
---------------------------------------------------------------------
◎体重を計測しましょう。あなたの適正体重は?
適正体重=(身長m)²×22
例えば、身長160cmの人なら、1.6×1.6×22=56kg
---------------------------------------------------------------------
適切な体重を保つために以下を心掛けましょう。
①バランスの良い食事
②油物は控えめに
③免疫機能を高めるために腸内環境を改善。発酵食品や、食物繊維をたっぷりと
④抗酸化作用のある食品を積極的に
⑤もちろん運動も!
2020年9月広報誌掲載
まだまだ残暑が続いていますが、水分は摂れていますか? 涼しくなると安心して水分が減り、脱水や熱中症になる方が多いと言われています。
脱水予防のための目安量としては一日最低でも1ℓで、「食事(間食含む)+飲み物」で約2ℓ といわれています。一度に大量の水分を摂ると心臓や腎臓に負担をかける可能性があるので、回数を分けて少しずつ行うことがポイントです。
しかし、口当たりの良いジュースやスポーツドリンクを飲み過ぎてしまうと、「ペットボトル症候群(ソフトドリンクケトーシス)」を起こす恐れがあります。砂糖を多く含む飲み物を多飲することで起こる急性の糖尿病のことです。(角砂糖で例えるとコーラには約15個分、スポーツドリンクには約9個分が入っています)
おすすめは常温で水や麦茶のように砂糖の入っていない飲み物です。冷たい飲み物を摂り過ぎると、内臓が冷えて体温が低下し、代謝が悪くなる原因になるので注意しましょう。
2020年7月広報誌掲載
「食品添加物」というと、体に良くない物というイメージを持っている方もいるかと思います。しかし、現代の加工食品には多く使用されています。今回は「食品添加物」とはどのようなものかを紹介します。
「食品添加物」は、食品衛生法において、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」が定められています。代表的な添加物を紹介します。
甘味料...食品に甘みを与える
着色料...食品を着色し、色調を調整する
保存料...カビや細菌などの発育を抑制し、食品の保存性をよくする
増粘剤、ゲル化剤...食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、分離を防止し、安定性を向上させる
酸化防止剤...油脂などの酸化を防ぎ保存性をよくする
食品を長持ちさせ、より美味しくする役目があります。添加する目的を知り、消費者の私たちが賢く、上手に付き合っていくと良いですね。
2020年5月広報誌掲載
近年、カリウム摂取による骨の健康への有用性が報告されており、骨粗しょう症の予防効果が期待されています。
理由は、カリウムの摂取量が増えることで、カルシウムの排泄量が減少するためと考えられています。また、ナトリウムの過剰摂取は尿中のカルシウム排泄量を増やすことも広く知られており、ナトリウム排出効果のあるカリウムを多く摂取することは骨の健康に重要です。
カリウムを多く含む食品は、新鮮な野菜、果物、海藻、キノコ類など。積極的に摂取しましょう。
2020年3月号広報誌掲載
油を選んで賢くとろう!
CMやスーパーで様々な種類の油を見ることが多くなっています。
それぞれの特徴を知って上手く使うことで、体に良い効果が期待できます。
しかし、摂り過ぎてしまうと肥満の原因となるっため注意しましょう。
| えごま油 | 亜麻仁油 | オリーブ油 |
原料 | しそ科のえごま | 亜麻(植物の種子) | オリーブ |
| ・α-リノレン酸が豊富 ・熱に弱く酸化しやすく、和え物等加熱せずに使用がおすすめ | ・α-リノレン酸が豊富 ・熱に弱く酸化しやすく、和え物等加熱せずに使用がおすすめ | ・オレイン酸が豊富 ・光や空気にふれると風味が変わるため、暗所での保存が良い |
(α-リノレン酸、オレイン酸とは?)
油脂は構成成分により飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分類されます。
これらは不飽和脂肪酸で、悪玉コレステロールを下げ、動脈硬化を予防する働きがあります。
飽和脂肪酸は、過剰摂取により悪玉コレステロールが上昇、動脈硬化性疾患の原因となります。
2020年1月号広報誌掲載
腸内環境を整え、インフルエンザや風邪に負けない体づくり!
冬は空気が乾燥して、風邪やインフルエンザにかかるリスクも高まります。免疫力をアップさせるには善玉菌を増やし、腸内環境を整えることが大切です。
善玉菌を増やすためには、「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」が含まれた食べ物を日常的に摂ると効果的です。最近話題の「シンバイオテックス」は2つを組み合わせたもので、同時に摂取するとより効果的であると考えられています。
プロバイオティクス | 腸内細菌のバランスを整える乳酸菌などの微生物 | 発酵食品 ヨーグルト、納豆、味噌、チーズなど |
プレバイオティクス | 「プロバイオティクス」のエサになり、善玉菌を増やす働きのある食品成分 | オリゴ糖や食物繊維 野菜類、いも類、豆類など |
他にも、バランスの良い食事を摂り、ストレス、睡眠不足に気を付けることも大切です。腸内環境を整えて、病気に負けない体をつくりましょう。
2019年11月号広報誌掲載
旬に食べよう!
食材の最もおいしく、沢山取れる時季を「旬」といいます。四季のある日本では昔から「旬のものを食べるとカラダによい」と言われてきました。これは、沢山出回るから安価でおいしいだけではありません。
ほうれん草を例に挙げると、ほうれん草100g中のビタミンC含有量は年間平均35mgですが、夏取りでは20mg、最盛期を冬取りは60mgと大きく差があります。旬のものを食べるということは、食材から季節を感じられ、栄養価の面でも私たちに大きなメリットがあります。
2019年9月号広報誌掲載
災害時の非常食について
9/1は防災の日です。この機会にご自宅の「非常食」を見直してはいかがでしょうか?
「非常食」としてよく売られているのは、5年程度の長期保存が可能な食べ物や飲み物。
これだけだと選択肢は限られますが、スーパーなどで手に入りやすい食品にも非常食となるものが多くあります。食べ慣れたものや自分の好みに合う食品で揃えられるという良い点があります。
□レトルト食品
例:レトルトのカレーやシチュー、ハンバーグ
(製造過程で加熱しており、そのまま食べることが可能な食品もあります)
□インスタント食品
例:カップ麺、みそ汁
□フリーズドライ食品
例:フリーズドライご飯(炒飯やチキンライスなどたくさんの種類があります)
□缶詰製品
例:ツナ缶、さば缶、鮭缶、果物缶
□乾物
例:ドライフルーツ
「非常食」と比べると賞味期限は短いので、備蓄している食品を定期的に食べ、食べた分を買い足していく「ローリングストック」などで上手に保管しましょう。
2019年7月号広報誌掲載
フレイル予防~元気で長生きするための食事~
フレイルとは心と体の働きが弱くなってきた状態(虚弱)を言います。
人は年を重ねると体の力が弱くなり、外出する機会が減り、徐々に要介護状態に陥ると考えられています。
フレイルを予防するためには運動、社会参加が重要ですが、今日は栄養についてお話しします。低栄養は、フレイルを起こす最大の要因です。高齢になり、食が細くなって、体を維持するために必要な栄養素が不足します。特に一人暮らしの高齢者は、食事の品数も減り、食べる食材も偏り、食欲が低下しがちで、低栄養状態に陥りやすくなります。
フレイル予防の食事のポイント
1日3食バランスよく食べましょう。
肉、魚、卵、豆腐(大豆製品)のタンパク質を毎食1品は食べましょう。
少量しか食べられない方は惣菜パン、おにぎり、ゼリーやプリン、ヨーグルトなどの間食、栄養補助食品を取り入れましょう。
※医師や管理栄養士の指示のもと食事の調整を行うようにしてください。
2019年5月号広報紙掲載
減塩とダイエット
成人男性が8.0g未満、女性が7.0g未満とされる1日の目標塩分摂取量。これは「日本人の食事摂取基準」の項目の1つとして、5年に一度検討され、厚生労働省から発表されたものです。しかし国民栄養調査によると、男性の1日平均塩分摂取量が10.8g、女性が9.1gと目標値を超えているのが現状です。
塩分の過剰摂取は高血圧の大きな原因であることは広く知られていますが、濃い味付けの食事は、ついついご飯やお酒がすすみ、肥満を助長します。
薄味の料理はおいしくないと思われがちですが、日ごろから薄味に心掛けることで舌は慣れていきます。そして、素材の味を活かした味付けをおいしいと感じるようになるはずです!
減塩はダイエット成功の大きな鍵。今日からぜひ実践してみてください。
2019年1月号広報紙掲載
年末年始はアルコールを飲む機会も多く、それに伴う体重増加が気になるところではないでしょうか。アルコール は1g7kcal と推定されます。しかし、アルコールの代謝は個人の能力によって異なり、実際は代謝の過程で熱を発し、エネルギー消費が増加します。そのため、太らないとも言われますが、真偽は定かではありません。
また、蒸留酒(焼酎、ウイスキー)は太らないが、醸造 酒(ビール、日本酒)は太ると言われる理由は、醸造酒が糖質を含んでいるためですが、ビール 500mlの糖質がごはん100g(おにぎり1 個分)と考えると、アルコール飲料だけで太るとは言いがたいところです。
お酒を飲んで太るのは、一緒に食べる食事が脂っこく高エネルギーで食事時間が長く、食事量が増えてしまうことが大きな原因と考えられます。宴席には、自制心をもって、臨んでくださいね。
2018年7月号広報紙掲載
ジメジメと暑い日が続き、食中毒が気になる今日この頃。お肉の種類によって日持ちに差があることをご存知でしょうか?
食用肉の中で最も痛みやすいのは鶏肉です。鶏肉は牛、豚に比較し、水分量が多く、雑菌が繁殖しやすいことが理由です。加工による違いでは、最も痛みやすいのが空気にふれる面積が多いひき肉で、次にスライス、ブロックの順に傷みやすくなります。保存のコツは、ラップを肉に密着させ、空気にふれさせないこと。もちろん、冷所保存、早めの調理を心がけましょう。
2018年5月号広報紙掲載
いつまでも美しく、美肌を保ちたい・・。私たち女性の永遠の願いですね。
肌には「ターンオーバー」という4週間で新しく生まれ変わる周期があり、これが円滑に行われば肌は美しい状態を保つことが出来ます。
そのためには肌の素となるたんぱく質をはじめ、ターンオーバーに必要なビタミンB群、ビタミンC、亜鉛、腸内環境を整える食物繊維などをしっかり摂る必要があります。そしてもうひとつ、「よく噛んでたべること」が重要です。よく噛むことで唾液の分泌が促されます。唾液には成長ホルモンの1種で若返りホルモンと言われる「パロチン」が含まれ、肌にツヤを与えてくれるのです。
その他、保湿、メイクをしっかり落とす、皮脂が溜まらないようにするなどの外側からのケアももちろんお忘れのないように。
2018年3月号広報紙掲載
テレビCMでも見かける話題のMCTオイル(Medium Chain Triglycerides)とは、ココナッツオイルから中鎖脂肪酸のみを抽出した100%中鎖脂肪酸のオイルのことです。一般的な油(長鎖脂肪酸)とは消化・吸収経路が異なり、分解速度が速く短時間でエネルギーになることが特徴です。
高齢者の低栄養改善、アルツハイマー型認知症の改善効果があるとされ、さらにダイエット効果から生活習慣病の改善にも期待される今注目の油です。
その特徴から、「体脂肪になりにくい」、「ケトン生成による痩せる効果」は期待されますが、「食べたものを吸収させない」、「食べた物のカロリーを無くす」といった効果はありません。
痩せたいからといって、たくさん摂ればいいというものではなく、いつもの油をMCTオイルに変える程度の使い方にとどめましょう。
2018年1月号広報紙掲載
たくさん歩く人ほどHDLコレステロールが高い
厚生労働省の調査によると、1日の歩数の多い人ほどHDL(善玉)コレステロールが高く、1万歩以上歩いている人と、そうでない人では10%以上の差があると報告されています。
HDLコレステロールの値が低くなると、血液中に余分なコレステロールが増加し、動脈硬化のリスクが高まります。原因としては、喫煙、肥満、運動不足がHDLコレステロールを低下させることが分かっています。
1日1万歩程度の適度な運動は、中性脂肪低下、LDL(悪玉)コレステロールの低下、HDLコレステロールの上昇が期待できます。
また、最近の研究では、食品に含まれるコレステロールは血中脂質に「ほぼ影響しない」とされ、日本人の食事摂取基準(2015年度版)からはコレステロールの摂取上限が撤廃されました。しかし、食べ過ぎによる内蔵型肥満はさまざまな病気の原因となります。
適度な運動、腹八分目の食事が健康管理の基本と言えますね。
2017年7月号広報紙掲載
肉と魚で違う 塩をふるタイミング
魚の塩焼きは、表面に塩をふることで、塩味をつけるのはもちろん、塩が身の生臭みを水分として外に出し、身が引き締まり崩れにくくしてくれます。魚の塩は、ふってから20分おき、出た水分をよくふき取ってから焼くと、おいしく焼き上がります。
一方、魚と違い柔らかく仕上げたい肉は、焼く直前に塩ふった方がおいしく焼き上がります。肉は塩をふって時間が経つと、水分が出て固く、うまみが抜けてしまいます。
また、肉も魚も精製塩より天然塩の方が、塩気がまろやかにおいしく仕上がります。まんべんなく塩をふるには、材料の20~30cm上からふってみてください。バーベキューシーズンに、ぜひお試しあれ。
2017年5月号広報紙掲載
トマトの栽培時期は2期に分けられ、ハウス栽培が中心の冬春トマトと露地栽培が中心の夏秋トマトがあります。冬春トマトは甘みが強く、夏秋トマトは酸味が強いのが特徴です。真夏のイメージのトマトですが、実は高温多湿を嫌います。日射しは強く、気温はそれほど上がらない4月~5月の頃のトマトが、糖度が高く旨みの強いトマトになります。
「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるように、栄養豊富なトマトの中でも特に注目されるが、赤い色素のリコピンです。リコピンはカルテノイドの一種で、有害な活性酸素の働きを抑える強い抗酸化作用を持ちます。 その働きはβ‐カロテンの2倍、ビタミンEの100倍もあり、がん予防、生活習慣病予防、アンチエイジングに期待されています。
農協の直売所にもさまざまな種類のおいしいトマトが並ぶこの時期、旬を逃さずお召し上がりください。
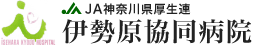


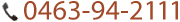


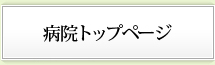



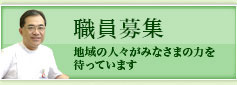
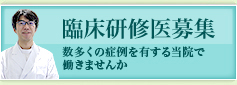
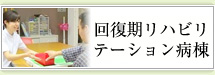


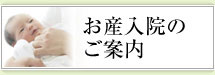
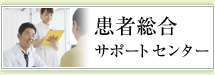
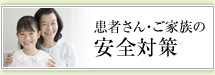
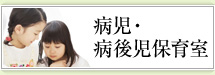



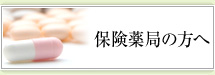
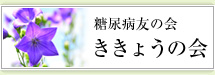


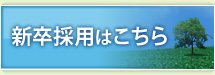

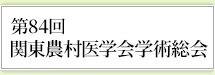


















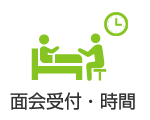

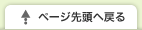
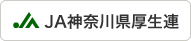

ついつい忙しいからと早食いになっていませんか?早食いは太るといわれていますが、本当でしょうか。
早食いと肥満の関係と、ゆっくり食事を取るためのコツを紹介します。
①早食いが太る理由
満腹中枢が脳に届くまで15分から20分かかるため、必要以上の量を食べてしまうことで肥満に繋がります。早食いは肥満以外でも、血糖値の急上昇や消化吸収不良が起こるなどのデメリットもあります。
★こんな人は注意!
ながら食いをする
他人よりも食事を終えるのが早い
飲み物で食べ物を流し込む
②ゆっくり食事を摂るためのコツ
1.食物繊維の多い食品や固い食品を食べる
2.野菜類を先に食べる
3.野菜を大きめに切る
4.小さいスプーンを使用し、一口30回噛むようにする
5.食事の10分前にガムを噛んで満腹中枢を刺激しておく
健康の維持増進のためにもよく噛んでゆっくり、味わって食べましょう。